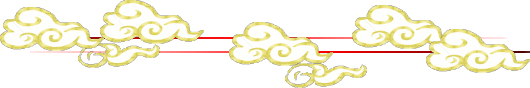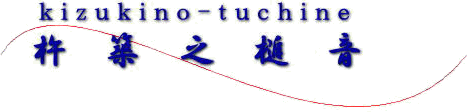1. 柱脚遺構の出現Excavation of column pillar remains
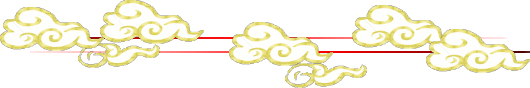
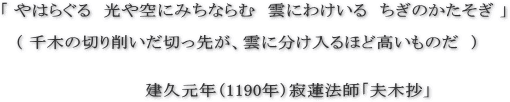
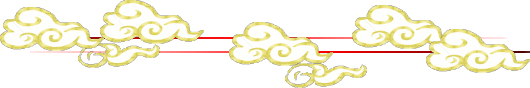
遥か昔、出雲大社は今よりもずっと高く聳えていたという
言い伝えがありました。
しかし、それはあくまでも伝説の域を出ない話としてしか
語られることはありませんでした。
多くの歴史学者、建築学者、日本史研究家などの間に
おいても、信憑性の無い説としてしか扱われることは
ありませんでした。


ところが、2000年、
本殿境内の地下に祭礼準備
室を作るための発掘調査を
行っていたところ、
思いがけず巨大な柱脚の
遺構が現れたのです。
それは、1本約直径1.4m杉の木を三本束ねて一本にした
総直径3mもの巨大な柱でした。
続けて他所からも二か所同様な構造の遺構が出土しました。
そしてそれは、調査の結果、鎌倉時代前半(宝治2年
=1248年頃)の本殿のものと推測されたのです。

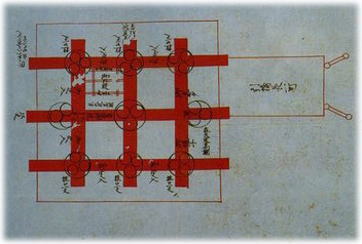
発掘された柱の
大きさや構造、
そして位置関係
が、驚くべき
ことに出雲国造
千家に伝わって
いる古文書
「金輪御造営差図」
と完全に一致したことにより、伝説としてしか語られて
こなかった古代出雲大社神殿が、
実在した可能性がにわかに高くなったのです。
■ 上図:出雲国造千家所蔵 「金輪御造営差図」

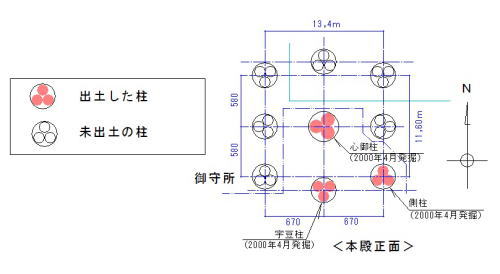
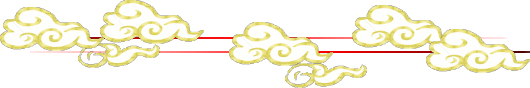
中古の時代、出雲大社は16丈(48m)あったとされ、
さらに上古の時代には32丈(96m)あったとされて
いました。(本居宣長の「玉勝間」)
(*中古とは概ね平安・鎌倉時代、上古とは概ね古墳・
飛鳥時代の頃をさします。)
そして、「金輪御造営差図」によると、本殿へ至る曳橋の
長さは一町(108m)にも及ぶ壮大な建築物であったと
考えられます。
それまで伝説でしかなかった古代出雲大社が、
にわかに現実として再び私たちの前に姿を現したのです。